川崎病とは!?治療方法や入院期間は?完治までどのくらいかかるの?

子供がかかる病気の中で、注意すべき病気の1つに川崎病という病気があります。
友人の子供が川崎病になったと聞いた時は、本当に発症することがあるんだと驚きましたし、詳しく知って起きたいなと不安になりました。
そんな川崎病とはどんな病気なのか、治療方法や入院期間、完治までにはどのくらいかかるのか、完治後についてなど詳しくご紹介していきますね。
目次
川崎病とは…?
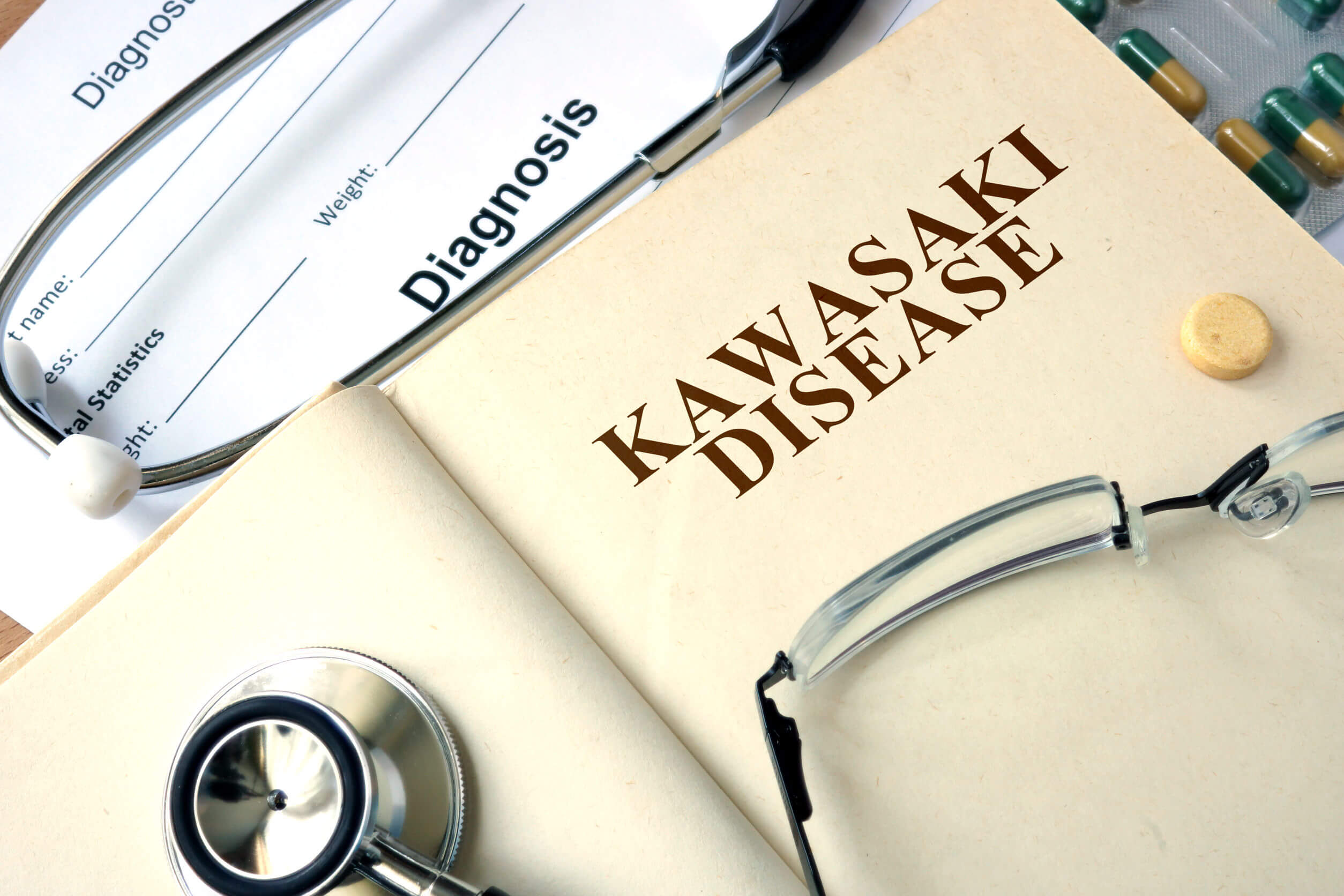
川崎病の正式名称は急性熱性皮膚粘膜リンパ線症候群といいいます。
全身の血管に炎症が起こります。
4歳以下の乳幼児が中心となり発症してしまう傾向があります。
特に、1歳前後の赤ちゃんによく多く発症します。
発症の原因は…?
発症の原因ははっきりとは分かっていないそうです。
しかし。感染症がきっかけとなり、過剰な免疫反応が起こることにより、炎症が起こるのではないかと考えられている病気です。
ウイルス、細菌などに感染した状態から体を守るために、免疫反応が起こるのですが、免疫反応が起こりすぎてしまうことにより組織が破壊されてしまい症状が引き起こるのですね。
症状は?!
川崎病の症状は、
急性期に38度以上の高熱が5日程続きます。
その後全身に赤い発疹、目の充血、唇の腫れ、手足のむくみなどが起こります。
症状には個人差があり、診断が難しくなる傾向があります。
また、症状が治まってからも、血管の炎症によりっ後遺症が残り、冠動脈瘤ができてしまうこともあり、場合によっては心筋梗塞が起こり死に至ってしまうこともあります。
注意が必要な病気なのですね。
川崎病は治るの?!治療方法は薬?

川崎病は回復にかかる期間に個人差があります。
しかし、発熱や発疹などの急性期の症状は治ります。
ところが急性期の症状はおさまったのにも関わらず、200人に1人は後遺症の冠動脈瘤を発症してしまうのです。
治療法は?
川崎病の原因がはっきりとしていないため、根本的な治療法がないのです。
しかし、最大の治療としては冠動脈瘤を発症させないようにすることとなります。
急性期の炎症が強く発熱が長引いてしまうことにより、冠動脈瘤ができやすくなってしまいます。
そのため、急性期症状はできるだけ早く悪化させないように血管の炎症を抑えるための治療が行われることとなります。
炎症を鎮めるために、免疫グロブリンと呼ばれている血液製剤が投与されることとなります。
そのため、川崎病と診断が出たら原則としてすぐに入院による治療となります。
また、急性期に血液が固まらないようにするために、経口薬としてアスピリンを処方され服用します。
そうすることで血栓や冠動脈瘤を予防することとなります。
急性期が過ぎた後は、冠動脈瘤を予防するための投薬と経過観察が続きます。
できるだけの治療を受けても、冠動脈瘤ができてしまったという場合は、精密検査の上で冠動脈瘤が大きく、冠動脈が狭くなってしまっている場合は、バイパス手術が必要となります。
川崎病の入院期間はどのくらい?
川崎病の入院期間としては、まずは病院で検査が行われ、肝機能、炎症反応を示す数値などの検査が行われます。
白血球の数も調べられますね。
その後、心臓の超音波検査が行われ、入院となります。
冠動脈瘤は川崎病の発症から1,2週間後に大きくなる傾向があります。
その後、数週間でピークに至るため、経過観察のためにも約2、3週間の入院が必要となります。
川崎病の治療期間は?完治までどのくらい?

川崎病の急性期の症状は通常1、2週間ほどかかり回復します。
しかし急性期の症状には個人差があり、症状が強く現れている場合は、完治までに1ヶ月ほどかかることもあります。
また、急性期がおさまってからも検査と経過観察が必要となることが多いものの、期間は病院によって異なります。
一方で、日本川崎病研究会運営委員会により川崎病の管理基準としては以下の通りの方針となります。
冠動脈瘤ができてしまった場合
冠動脈瘤ができてしまった場合は、冠動脈瘤の大きさにもよります。
しかし、動脈瘤が小さくなるまでは血栓を防ぐための投薬が続けられます。
1ヶ月ごとほどの頻度で投薬となり、そのタイミングで小児循環器医により経過観察が行われます。
心電図とエコー検査により確認されます。
経過観察と投薬を続けていても冠動脈瘤が大きいという場合は冠動脈造影も行われることがあります。
冠動脈瘤がない場合は
急性期の症状が収まり、その後の検査で冠動脈瘤ができていないという場合は、症状は収まってからも2、3ヶ月の間はアスピリンの投与が続きます。
その後、年に1回の心エコー検査を受け、約5年間ほどは経過観察を受けることとなります。
問題がないと診断された場合は薬の服用が終わります。
慎重な検査と医師の診断により治療期間が異なり、長期に渡り異常が起こっていないか確認していく必要がある病気ですね。
川崎病は治ってからも注意が必要

川崎病は治ってからも注意が必要です。
川崎病に罹ってしまうと、急性期の症状も辛く大変なのですが、症状がおさまってからも安心はできません。
冠動脈瘤ができてしまうことがあり、冠動脈瘤ができてしまった場合は合併症が起こってしまいます。
動脈瘤の中に血栓ができてしまい、心筋梗塞が起こるのです。
心筋梗塞を早期発見し対処するためにも退院後も油断せずに検査を受けることが大切になります。
時に命に関わる重大な病気であるため、甘く見ず慎重に治療や検査を受け続ける必要がありますね。
治療が終わってからも定期検診をしっかりと受けることが大切ですね。
まとめ
川崎病が発症しても現在の医学の発展により、冠動脈瘤が出来る可能性は低くなってきています。
しかし、やはりゼロ出はなく、時に治療後に心筋梗塞が起こってしまうこともあります。
冠動脈瘤が起きなければ、治療後の経過が良好であれば日常生活に支障なく過ごすことるので、早く異変に気づき、早急に治療を受けることが大切ですね。
高熱が続き下がらない、発疹が見られるなどの症状が見られた時は小児科に受診ししっかりと診断を受け治療を受けましょう。
